合言葉は「世代間移動」
2015年1月1日施行、相続税改正をうけ、相続税課税割合は倍増(下のグラフ参照)。基礎控除が4割圧縮されたことの影響の大きさを見ることができる。
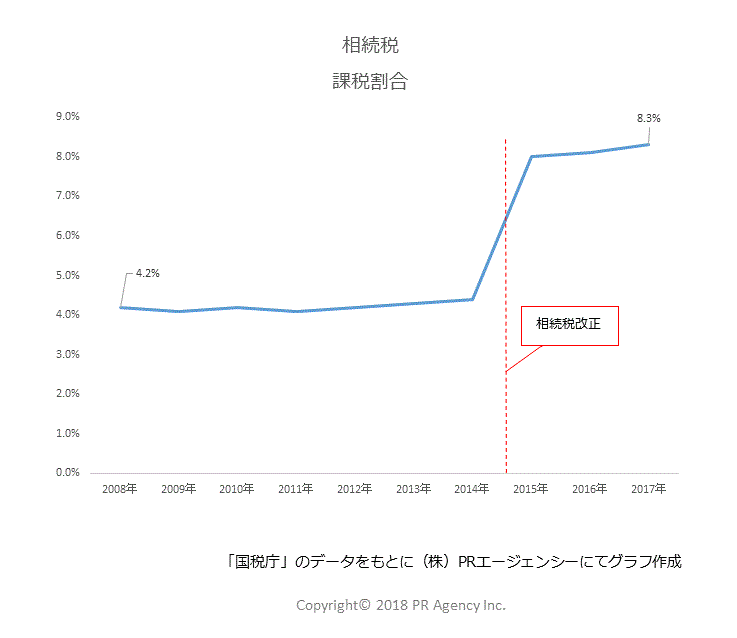
相続税の課税割合
一方、相続税改正が告知(公布)された段階(2013年3月30日)から不動産マーケット、なかでも「マンション市場」に「節税対策目的の資金が流れ込んできた」のが、国交省発表「不動産価格指数」推移(下のグラフ)でわかる。
制度改正がなされる前からマーケットが反応した。それだけインパクトがあったということ。「税の改正」が不動産市場にいかに影響をもたらし、またそれが継続している様子が伺える。
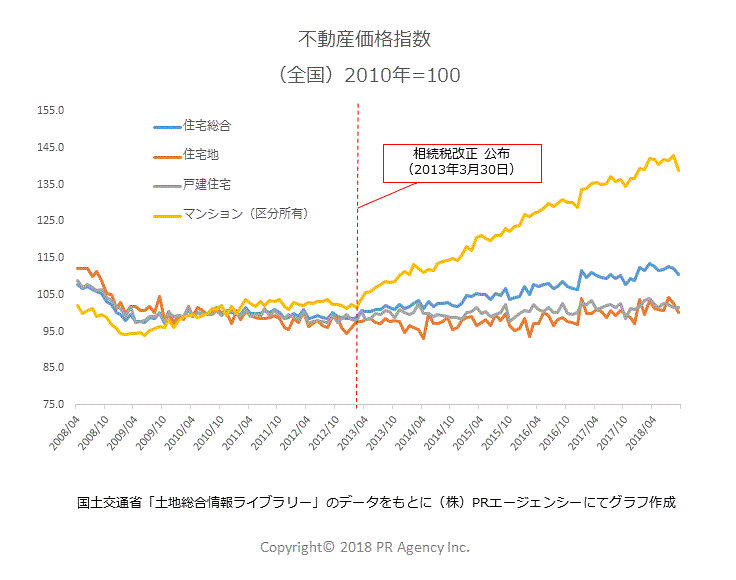
資産の世代間移動は、日本全体の課題。賃金が増えない働き手にマイホーム資金をまわし、経済の活性化を促そうとする試みは、一石三鳥といえるだろう。コンパクトシティ構想の象徴のような「駅近大規模物件」、官民共同作ともいえる「再開発プロジェクト」にそれが向きやすいというのも想定のうちか。いずれにしても、ベクトルはすべて同じと言えなくない。
消費増税をさらなる機会に
さて、いよいよ10月に消費税が10%に引き上げられる。2度の延期により、景気腰折れ懸念を払しょくするための万全の対策が取られた、という印象だ。住宅ローン控除の拡充は増税分(2%)に留まったのだが、住宅取得等資金贈与の非課税枠の大幅拡充がそれである。
住宅取得等資金贈与の非課税枠は、リーマンショック後の景気低迷を打破するために導入された施策。当初(2009年)500万円だったのを2010年1500万に引き上げた。この効果は、住宅市場に前年比5281億円増(非課税適用分)の資金を提供した。同3.7倍である。申告人員は3万人増である(下のグラフ参照)。
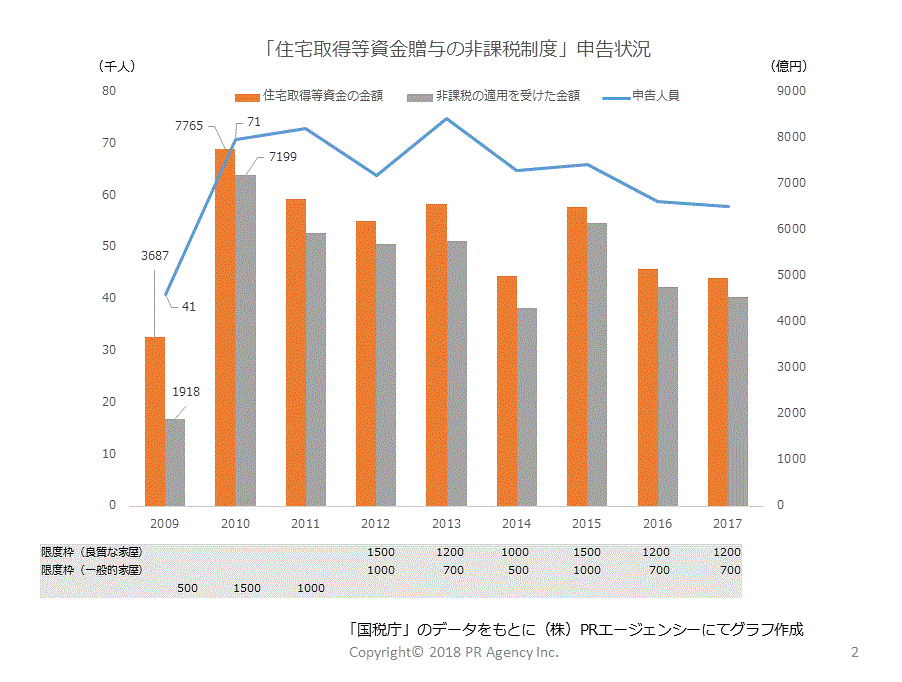
追い風が吹きやすい物件は?
消費税10%が適用される住宅の購入に際しては、「住宅取得等資金贈与の非課税枠」が2019年4月1日から2020年3月31日(契約締結)は3000万円(省エネ等住宅)それ以外の住宅は2500万円になる。次の年度はそれぞれ1500万円と1000万円。よって、2019年度に消費税が適用される「住宅事業者売主の物件」には神風が吹く?かもしれない。
贈与する側が「その物件なら」と思わせる「立地の良さ」「建物の質」が求められるのではないだろうか。
それらはマーケットデータを牽引するカテゴリーに比較的合致するとみている。したがって、直接的な恩恵を享受しなくとも「市況データは悪くなさそうだ」というムードが醸成されれば、すべての不動産物件にプラスの材料となりうるだろう。超低金利が慢性化したいま、市場動向は「税」次第ともいえる。