都心3区、城西地区は「成約単価」記録更新
下のグラフは、23区の中古マンション「地区別 成約単価」推移である(「東日本不動産流通機構」発表)。都心3区、城西地区は2019年11月度、最高値を更新した。城北地区は前月同じく高値を付けている。
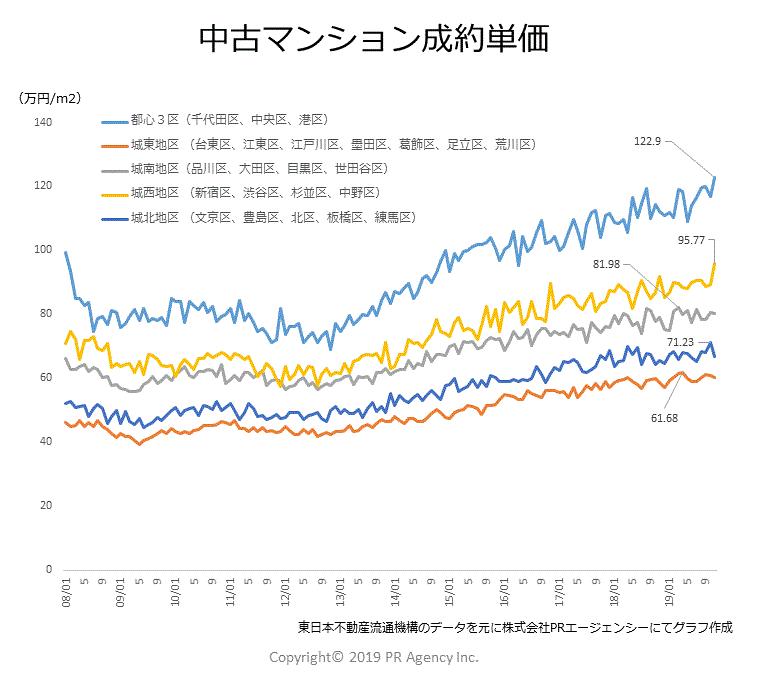
地区全体が上昇しているわけではない
たびたび掲載している「中古マンション成約単価」であるが、ここであらためて「データの意味と相場観」について触れておきたい。データの意味とは、東日本不動産流通機構が発表する成約単価はあくまで「成約した物件の単価」である。都心3区が高値を更新したからと言って、すべての同地区のマンションが値段が上がっていると捉えてはいけない。
地価データでいえば、「路線価」や「基準地価」は、そのときどき(年)による景況や状況・環境を考慮して、相場全体の動向を示し「不動産取引の目安」となるものだ。租税の元になるものでもある。
取引される物件の特徴を理解すること
したがって、公的データである「路線価」や「基準地価」は市場動向を俯瞰して見る、または地域間での変動の違いを見る、等には適していいる。
しかし、東日本不動産流通機構調べの「中古マンション 成約単価」は取引が実際にあった物件の単価であるから、取引そのものが活発化していたり、逆に減退している物件の特性があれば、まずそれを加味する必要がある。
例えば、旧耐震(耐震基準を満たしていない)マンションが法改正や仲介会社の方針、またはファイナンスの関係で市場競争力を失っていたとする。一方、同じく相続税改正や超低金利等による環境の変化で築浅のタワー上層階に引き合いが強い状態が継続している。といった極端な情勢に至った場合、成約単価の引き上げは、そのエリア全体のマンション需要が高まっていると捉えることもできるのであるが、より正確に表現すると「一部の富裕層が節税目的あるいは余裕資金の運用先の行き場として、好立地で好条件のマンションを求め、それが全体の取引データを引き上げている」となる。データの捉え方を誤ると判断ミスを犯しかねないから注意が必要だ。